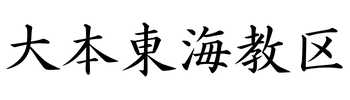日本社会では、「空気を読む」ことが美徳とされています。相手の気持ちや場の雰囲気を察して行動することは、対立を避け、円滑な人間関係を築く上で確かに重要な能力といえるでしょう。
しかし、この「空気」が時に冷静な事実やデータを押し流し、集団ヒステリーや過剰な弾圧へと発展する危険性があることも、歴史が示しています。
例えば、コロナ禍においては、実際のリスクを超える「自粛ムード」が社会を覆いました。
SNS上では「自粛警察」と呼ばれる人々が他者の行動を非難し、屋外でのマスク着用など、科学的合理性に欠ける行動が日常化しました。
空気が個人の判断を抑圧し、社会全体が感情的な空気に飲み込まれていった状況は、まさにその典型だったといえます。
さらに、厚生労働省が公表する新型コロナワクチンの副反応データでは、2024年時点で2000件を超える死亡事例が報告されています。
しかし、当時は「安全性を疑うこと自体が不適切」とする空気が支配的となり、リスクについて冷静に議論することが困難な状況が続きました。
科学的なリスクコミュニケーションよりも、空気による同調が優先され、異論が封じられるような雰囲気が広がっていたことは否めません。
このような『空気による支配』が国家レベルで暴走した典型例が、近代日本最大の宗教弾圧ともいわれる『大本事件』です。
昭和初期、大本は急速に勢力を伸ばし、革新的な教義や社会活動によって注目を集めました。
しかし、当時の国家権力は『社会秩序を乱す』『国体に反する』といった批判的な世論を意図的に煽り、事実の検証を行わないまま、治安維持法違反や不敬罪を理由に、教団施設の破壊や信徒の大量逮捕等、苛烈な弾圧に踏み切りました。
言論統制が進む中で、マスメディアも追随し、真実は報じられませんでした。国民世論もこれに同調し、異論を唱える声はほとんど聞かれなくなっていきました。

その後、治安維持法違反に対する無罪判決が下されたものの、この重要な事実も報じられることはなく、大本は「邪教」として長年にわたり誤解され続けます。
大本事件は、国家権力と世論が一体化したときに、いかに恐ろしい集団心理が生まれるのかを、私たちに改めて問いかけています。
こうした過ちを繰り返さないためには、私たち一人ひとりが、空気や感情に流されることなく、冷静に事実やデータに向き合う姿勢を忘れてはならないのではないでしょうか。無理に考えや価値観を押しつけることは、必ず後で悪い結果を招きます。相手が納得し、理解できるよう工夫することは建設的ですが、ただ自分の主張を通すために争うのは愚かなことです。
天地万物、人間一人ひとりには、それぞれ異なる役割や特質があります。それを無視して、すべてを自分と同じにしようとするのは、自然の摂理を歪める行為といえます。
相手を導くことは大切ですが、強制することは違います。「導く」とは、相手の本来の性質を尊重し、その能力を引き出し、成長を助けることです。一方で「強いる」とは、相手の性質を無視し、自分の思い通りに変えようとすることです。
相手の心に「こうありたい」「こうなるべきだ」という思いがなければ、たとえ正しいことを与えても、それは猫に小判、馬の耳に念仏に終わります。かえって迷惑になるだけで、喜ばれることは決してありません。
空気に流されず、事実と理性を重んじる。相手の尊厳を尊重し、対話を重ねる。そうした姿勢こそが、感情に支配されずに健全な社会を築く礎となるのではないでしょうか。
メディアの責任
こうした社会を築くには、何よりもまず「違いを受け入れる力」を育む教育が求められます。学校では、単に知識を伝えるだけでなく、異なる価値観や背景を持つ他者と対話する力を養うことが重要です。他者の考えに耳を傾け、自らの意見を整理して伝える――そうした経験の積み重ねが、空気に流されにくい個人を育ててゆきます。
同様に、メディアにも果たすべき役割があります。現代において、メディアは「空気」をつくる最大の力を持つ存在です。新聞やテレビだけでなく、SNSも含めて、私たちの認識や判断を大きく左右しています。だからこそ、メディアは迎合的であってはならず、事実に基づいた冷静な報道を粘り強く続けることが求められます。
センセーショナルな話題や多数派の声、権力者の利益に偏ることなく、目立たない意見や慎重な主張にも耳を傾け、公平に伝えること。それが、情報が感情や空気に支配されるのを防ぐ第一歩です。
大本事件の際、マスメディアが国家権力に屈し、批判的報道を封じた歴史は、まさにその逆を示すものでした。真実は歪められ、異なる声は切り捨てられました。そしてこの構図は、コロナ禍にも繰り返されました。ワクチンに対する異論や疑問を「非科学的」「反社会的」と断じ、議論を封じる偏向報道は、今なお続いています。
本来、メディアの使命は世論に従うことではなく、世論を問うことです。社会にあふれる声をそのまま反映するのではなく、時に問い直し、足元を照らす。そうして透明性と多様性を守ることが、健全な民主主義と理性的な社会の礎となるのではないでしょうか。
大本のお示し
あえて争うということほどバカ気がことはない。無理に強いるということは、かならず、あとに悪い結果をのこすものである。相手を心から合点さし、理解さすようにと、いろいろ手段を弄するのはよいことである。そうでなくして、ただ単に、自己を主張するために争うというのは愚の極みだ。なんら得るところがないからである。(『信仰覚書』第四巻 出口日出麿著)
天地万物一切のもの、また人間各自それぞれに、異なった機能なり特質なりを持っているのに、僭越にも一切を自己の如くにあらしめんと計るというのは、あきらかに神を涜(けが)すものである。すべて物事をみちびくということは、甚だ良いことであるが、これを強いるということは全然いけない。導くというのは、相手の本性にしたごうて、これを覚まし伸ばしてやることであって、強いるというのは、本性を無視して、急激に自己の欲するままにならしめんとすることである。その人の意志に、こうあるべきである。こうありたい、と、まず念じたことでなくては、いくら第三者から見て真(善美)なりとするものを与えても、いわゆる猫に小判、豚に真珠の結果におわるだけである。相手は迷惑こそすれ、決して喜ぶものではない。
世の中には、自分は聖人君子のごとき行いをしているのに、他の者はみな、詐欺や泥棒ばかりである。自分はこんな礼儀ただしく、義理を重んじているのに、ほかの者はみな不作法であり、義理知らずである――といって、自分だけは正しい、他人はみな間違っている、と考えている道学者流の人間も随分おおい。かかる人には、他をみちびく資格は断じてないと思う。なぜなれば、すでにその人の心境において、自分以外の一切を否定し、排除せんとする傾向が濃厚であるからである。すなわち、自分のごとくにある者は愛するが、自分のごとくにない者は、これを愛せないというのではなく、これを憎むのだからたまらない。(『信仰雑話』出口日出麿著)
東海教区特派宣伝使 前田 茂太