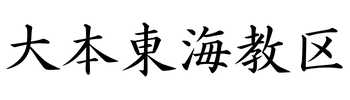命の話をする時、どうしても避けて通れないのが「食べること」。
毎日あたり前のようにしているこの行為は、実は私たちの血管を、心臓を、そして寿命を静かに左右しています。今日は、そんな命に関わる「食」と「動脈硬化」の関係について、少しだけ深くお話ししてみたいと思います。
出口王仁三郎聖師の健康法に関するお示しを集めた選集「愛善健康法」には、このように記されています
「動脈硬化症より免れようとする者は、断然、肉食をよして、菜食に移らねばならぬ。魚類等もなるべくさけたがよい。ことに刺身の類はよろしくない。たまにアッサリした川魚ぐらいは食べてもよい。元来、世人は、肉類魚類には多大の滋養分があるように思っているが、真の滋養価は野菜が一番である。かなり大きい鯛と、大きな大根一本と相当するくらいなものである。」(選集「愛善健康法」について詳しく見る)
ここで語られているのは、「血管の老化」から身を守るための食の選択。
私たちはつい、肉や魚には力がある、エネルギーになると信じ込んでしまいますが、血管という目に見えにくい器官には、それが逆に負担になることもあるのです。
脂質の多い肉類や一部の魚類、特に刺身などの生魚は、時に血液をドロドロにし、動脈の壁を傷つけてしまうことがあります。
では何を食べればよいのか?
そのヒントは「川魚」と「大根」にあります。
川魚の優しさ
川魚は海魚に比べて脂質が少なく、EPAやDHAといった不飽和脂肪酸のバランスも軽やかです。DHAは脳や目の健康維持に欠かせない成分で、集中力アップや記憶力のサポートに役立ちます。一方、EPAは血液をサラサラにし、中性脂肪の低下に貢献することで、生活習慣病の予防につながります。
例えば、アユ、ヤマメ、イワナといった川魚は、あっさりとした味わいで、胃腸に優しく、消化に良いとされます。さらに、自然の清流で育った川魚はストレスが少なく、肉質もやわらかです。そのため、脂のしつこさがなく、心臓や血管にも穏やかに作用します。
これに対し、海の深部を回遊する魚は脂が濃く、それがコレステロールや中性脂肪の増加につながることもあります。「たまにはあっさりした川魚を食べるのが良い」と言われるのは、このような背景があるのかもしれません。
大根の底力
大根は、単なる脇役ではありません。
・ジアスターゼ(消化酵素)
・ビタミンC
・食物繊維
・カリウム(ナトリウム排出)
これらが詰まった「血液さらさら野菜」といってもいい存在です。
とくに大根に含まれる辛み成分「イソチオシアネート」は、血栓を予防し、動脈硬化の原因になる血管内の炎症を鎮めてくれる力もあります。
しかも、煮ても良し、生でも良し、皮まで使える万能選手。
実はこの大根、滋養面では「かなり大きい鯛と、大きな大根一本と相当するくらい」だと言われています。
命を支えるのは、きらびやかな料理や派手な食材ではなく、こうした“地味な力”なのかもしれません。
今日も、あなたの血管にやさしい一日でありますように。