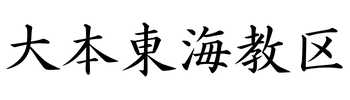大本三代教主補 出口日出麿
本名は、高見元男といい明治30(1897)年、岡山県倉敷で生まれました。幼少の頃より霊的感受性が強く、人生の壁にぶつかり神を求めた青年時代の悩みを記したものが『信仰覚書』と『生きがい』シリーズです。
大正8(1919)年岡山旧制六高在学中に大本に入信しました。大正13( 1924)年、現在の京都大学の前身となった京都帝国大学文学部中退しました。
昭和3(1928)年、大本三代教主出口直日と結婚。昭和10(1935)年に起こった第二次大本事件による弾圧で過酷な拷問を受けました。
大本事件後は大本教主を霊的に補佐し、万民の霊的救済に専念しました。著書に『信仰覚書(全8巻)』『生きがいの探求』『生きがいの創造』『生きがいの確信』などがあります。
ロサンゼルスオリンピック体操金メダリストの具志堅幸司選手は『生きがいの探求』『生きがいの創造』『生きがいの確信』(講談社)の3部作の熱読者として有名です。また、その半生が描かれた伝記『神仙の人・出口日出麿』(講談社)は、多くの人々に感銘を与えました。
『信仰覚書』から「霊界探検」の様子をご紹介します。
大神業も現界を基礎に
例の紋付の人がみちびくままに、私はたんたんたる大道を飛ぶように通って(飛ぶようにというのは、足は地の上に直接ついているのでなく、三尺ばかり上をスーッとすべるように過ぎて行くのである。この時はそうであったが、時によると、直接地上を普通に歩むこともあり、また場合によっては、空中を自体が飛ぶこともあり、また、ある鳥に乗ってゆくこともあり、何か大きな手に抱かれて一散にある地点に達していることもある。その、それぞれの理由はいろいろあるが、概して言えば、高い霊界ほど自由自在であり、低い世界ほど、一歩一歩、直接にあえぎあえぎ歩まねばならぬのである)。ある山麓に達した。
私「ここはどこです?」
天使「ひらおか」
私「どこの国です?」
天使「河内」
私は何心なく坂道を登った。すると中腹にあまり大きくない、どちらかと言えば、古ぼけた一つのお社があった。二人は問答をはじめた。
私「いったい人間は、何しに生まれたんです?」
天「神さまのご用しに……」
私「神さまはどこにいるんです?」
天「お前のまえに」
私「あなたは神さまですか?」
天「いや、わしはお使いだ。わしがおるとおらぬとにかかわらず、神さまはお前のまえにおられるのだ。しかし、わしがお前のまえにおる時は、よりはっきり、神さまはお前のまえにおられるのだ」
私「神さまのご用というのは何ですか」
天「一口にいうなら、各自(めんめ)に、ほんとの自分の心の声にしたがって、一歩一歩、精進したら、それでよいのだ」
私「では、誰でも神さまのご用を、知らず知らずしているんですな」
天「まあそうじゃ。がしかし、いまの世の人は、ほんとの自分の心の声と、それとは違った声とを混線してしまって、どちらがどちらやら、分からなくなってしまっているのが多い」
私「ほんとの自分の心の声というのは、どんなのです? 私には、ほんとの自分が分かりません。始終、グラついておるようにしか思えません」
天「そうむずかしく考えないでもよい。その時、その折のベストをつくし、最善さえしたらよい。誰でもみんな途中にあるんだから、行き着いたあとから考えると、過去はお恥ずかしいことばかりだ。あの時は、も少しうまくやったらよかったにとか、いまの智恵があったら、あんな失敗はしなかったにとか、と、いろいろと悔むかもしれぬが、それは致し方ないことである。一つずつ体験を重ねていって、次第に真に賢くなり、大きく広くなることができるのであって、最初からチットも間違わぬよう、狂わぬようやろうと思ってもダメのことだ。それはちょうど、相手から一度も叩かれずに撃剣の達人になろう、生まれてから一度も砂の味を知らずに横綱になろうとたくらむようなものだ。お前は、疑いもなく造られたものである。造られたものは、造った者の意のままになるより外はない。最初から完全を期することは誰だって出来ない。その時の最善と信ずる道を行ったらよいのだ。たとえ後になって、それが間違っていてもかまわない、そのために、外では得られないよい教訓をあがない得たのであるから。ところが、この場合、多くの人は、その唯一の教訓をつかまずに、ただ失望と後悔とばかりを得ているのだからたまらない」
私「でも、いまの世の多くの人は物質主義者であって、霊魂の存続などということは、まるで、迷信かなんぞのように思っているんですもの」
天「それが、まえ言った混戦だ。こんな人たちに対しては、いくら理屈をいってもダメだ」
私「なぜです?」
天「こちらの理屈と向こうの理屈とが違うからだ。赤ん坊の理屈と大人の理屈とは違い、小作人の理屈と地主の理屈とは違い、インド人の理屈と英国人の理屈とは、おうおうにして非常に違っているのだ」
私「神さまは全智全能なんですから、ひとつ、いまの世の学者たちに、霊界を見聞させてやったらいいでしょう」
天「見聞させてやっても、却って現界を混乱させてしまうまでだ。それに、大抵は浮浪霊のとりことなって彼らのおもちゃになるのがおちだ。というのは、彼らに真の信仰がなく、いまだ利己執着の念つよく、ややもすれば嫉妬、怨恨などの悪念がきざしがちであるからである。だいたい霊界は現界人に見聞さすことは非常な危険がともないがちだ。現界人は現界人として、ただ今の最善をつくしたらそれでよいのだ。もっとも、正しい霊覚は神格の内流である。霊眼霊耳にとらわれると迷信におちいりがちだ。すべて、理屈をこねまわしている間は、断じて分かっているのではない。このことは、よくよく心得ておくがよい」
私「では、神を信ぜず、霊界を認めぬ人たちを導くにはどうしたらよいでしょうか」
天「みちびく? そんなことが、くちばしの黄いろい、尻っペタの青いお前たちに出来てたるか」
語気が急にあらくなったので、心中いささか不快に感じながら私は神使の顔を凝視した。と同時に、おそろしく強い眼光に射返されて、私の身はちぢまってしまった。今まで慣れなれしく話していた私は、もう一言も発することができなかった。私は心中「悪うございました」とお詫びした。すると神使は、晴れ晴れとしたいつもの調子で語をつがれた。
天「いつもいう通り、自分が、自分がという気が先になっては、真に何ひとつ出来るものではない。神さまのお蔭で生かしていただいている。神さまのお蔭でさしていただくという気持を、どんな場合にでも失わぬようにせねばいけない。今から人を導くというようなことが、お前たちに出来てたまるものか。限りなく、上には上があるのだ。すすんでも進んでも進みきれないわれわれだ。天国から直接現界へ降りての仕組であるから、何ごとも惟神にまかして、その時その折の時局に最善をつくしたら、それで充分なのだ。大事なことは、かならず、神が肉体にかかってさすのだ。現界は霊界の胞衣であり、卵であり、苗代であり、設計図であり、鋳型であり、土台であって、霊界の一切はことごとくその基礎を現界においているのだ。だから、宇宙的大神業も、かならずや、その基礎をまず現界から固めてかからねばならぬのだ。人間一個についていうも同様であって、現界において、早く神第一の霊的生活にはいり得た人は、死後ただちに光の国に安住することができるが、いつまでも自己第一の物的生活を営んでいる人は、死後は実につまらない境涯にはいらなければならぬ。こちらへ来い!」
私はだまって従いて行った。ある穴の入り口に立った。中をのぞいて見ると、巡礼のような風体をした人たちが、いずれも淋しそうな顔付をして、何かブツブツ言いながら往来していた。非常に汚く臭かったが、しいて中に降りてゆくと、その時はもう神使の姿は見えなかった。小さい祠みたような建物のまえにみんなうずくまって礼拝していた。立てられたローソクの灯が気味わるくトロトロと燃えて、流れた蝋が黒ずんで、そこら一面、蛇の子がかさなり合っているように這うていた。
私は大急ぎでそこを過ぎて前方にすすむと、また登り坂になって、一方の出口へ出た。このトンネルのちょうど上方に普通のお宮があって、立派にお祀りしてあったが、ここへは誰もお参りしていなかった。
この時、天使が見えた。私「あの人たちはなんですか」
天「利欲一方の信仰は、ああいう状態にあるのだ。あの人たちは、まだ神第一ということが分からないのだ。すべては上から来るということが悟れぬのだ。そして遮二無二あせっているつもりで、実はおなじ穴の中でお百度をふんでいるのだ」
私「どうしたら外へ脱け出ることができるんでしょう?」
天「こんなことをしていても詰らない、こんな所はいやだ、という気持さえ充分わいたら、自然に上方に足が向くのだ。いやな所にいつまでも頑張っており、あくまでも義理立てをしたり、つまらないことに得意がっているなどは、まったくの偽善だ」
私「しかし現界では境遇上、いたし方なくいやな所におり、つまらないことをしておらねばならぬ場合が多うございますが……」
天「周囲の事情がそうなっている間は、その人にめぐりがあるからだ。覚悟と努力が足らぬために、脱け出られる境遇をも脱け出ずにあがいている人たちの方がずいぶん多い」(『信仰覚書』第六巻 出口日出麿著)
再び天使あらわる
重荷をおろしたように軽快な気分になっていると、そこへ例の天使が非常な速力で、次第に大きい光輪となってあらわれた。あたりの一切は急に昼のような明るさにつつまれた。
私はひれ伏して心の中で言った。「天使さま、有難うございます。あなたのお蔭で、こんなに明るくなりました」
すると、金の鈴をふるような声で天使は言われた。(今まで、この声は幾度となく聞いていたが、この時ほど透き通った金声を聞いたことはない。これはずっと後になって知ったのであるが、いま迄は、天使はわざと本体をあらわさずに、ある他の精霊の体をかりておられたのである。それは、最初から本体のままで現われては、到底、罪に汚れた者はその光に堪え得ないで、はね飛ばされてしまうからである)
「日に向かう者は照らさる。まだ旅は長い、第一義的に……」
やがて天使は、大火球となって飛び去った。その瞬間、小さい一火球が、私がかねて一時も早く着手したいと思っている向かいの岩の斜面へ飛び散った。すると、あざやかに「神」という字が、光で描き出されてきた。私は思わず天使のうしろ姿をふしおがんだ。
しかし、天使が去られたあとは、例によって、また淋しいものであった。それでも以前よりは、身体も軽く、腹にも力が出来てきたが、なんといっても自分のからだには、まだ鱗のようなシャツが、上層部が除かれただけで、過半は肉にくっついて残っている。それを見ると、私は自分ながら自分が憎いような、また腹立たしいような、悲しい淋しい、口おしい、恥ずかしい、やるせない気持で一杯になった。
しかしまた思い返すと、これもまたお慈悲の鞭だ、何かわけがあることであろう。この鱗のシャツが本来自分のものでないにせよ、あるにせよ、そんなことはどうでもよい。げんに自分がそれをまとっており、そして、見る人ごとに恥をさらしている以上は、自分の罪の結果でなくてはなんであろう。(『信仰覚書』第六巻 出口日出麿著)
再び天使との対話
「めぐりというものは何でございますか」
「前世における霊魂の罪障だ」
「なぜ誰にでも、自分の前世は何物であったかということが分からないのでしょうか」
「思い出すわけにはゆきませんでしょうか」
「現界において、去年の今月今日に自分は何をしたかということさえ、普通、思い出すになかなか困難であろう。前世において、自分は何の誰兵衛であり、どこに住んで、何をしたかというようなことを、はっきり意識していることは、一たん嬰児の境涯をへて来る現界人にはても困難だ」
「嬰児の時分は想い出す力がなくても、成長してのちに、ちっとは分かりませんですか」
「成長するにつれて、現界的な印象がいよいよ強く明瞭に頭にまぶれつくから、よけい前世のことなどは分からなくなる。しかし、なんとなく気持において、過去世における自分の境涯が想像されるような気がする時もあるものだ。ごくまれには、自分は前世には何の誰某であったと、先天的におぼえている人もある」
私はこの際、再生や分娩の神秘について、はっきり神使からお伺いしたいと、次からつぎへ
と出てくる疑問を整理しつつ、口をもぐもぐさしている間に、フッと神使のお姿は消えてなくなった。
俗に「消えてなくなるタバコの煙」ということがあるが、タバコの煙でも実際は消えてなくなるのではなくして、消えてどこかへ行くのである。いわんや天使においておやだ。実はあまり、よそへ行き方が早いので、消えたように感ずるまでで、霊体の往来は、いわば、電気のそれのようなものだ。
その時、ふと私は、すぐ足もとの、さっきはいった穴の中へ入りたいなという気になった。理智は瞬間、なぜあんな汚い所へはいる必要があるか、と抗議を申し込んだ。が、一方、はいりたいなという気(これは、どこから来る気だ? と咄嗟に、その時わたしは考えたが分からなかった)がますますつのってきて、嵐のように私を駆った。私はそれでも用心しつつ、そろそろ、穴道へさしかかった。
前の時よりも、心もち、穴の中が明るいように思えた。下へななめに降りきった所が広くなって、その奥に一段高く、くずれかかった木の祠がある。私は吸いつけられるようにその前まで来た。と、急に足がピタリと止まった。
私はこの時、心中、こんなうす汚い祠へ吸いよせられたことを心得ぬことに思ったので、一度こころみに、わざと反抗的態度に出てみてやれと、ある力に抗しつつ、少しあとしざりをしてみた。多少苦しいが、強いて後へさがれば、いくらでも出来るように思ったので、五、六歩ばかりで立ちどまった。
と、スルスルスルと電気にかかったように最初の位置まで引きよせられた。「なにクソッ!」とまた三、四歩さがって止まってみた。スルスルスルと、また引きよせられた。そして今度は、急に非常な重圧をからだに感じて、押さえつけられたようにヘタばってしまった。
「きたない祠だが、えらい力のある霊がおるな」と、私はグタリとなって感心した。
顔をあげて見ると、どこかで見たことのあるような、ないような、五十恰好の中背の男が祠をうしろに私の目前に直立している。「わしの顔をよく見い」
「どこかでお見かけしたようでございますが……」
「ウハヽヽヽ分からんか」
「……」
「少し変わっているだろう」
「ヘェ、……分かりませんな」
そのうちに、その人の面貌が急に色白く、そしてふくれてきた。(現界においても、こうした面貌の変化はおうおうあることであるが、普通に気がついていないまでで、よく注意していると分かることがある)
私には、直ぐそれと分かった。「ハハァ、あなたは枚岡神使さまでございますな。しかし、少し背恰好がちがいますな」
「わしの宿っている体は、この祠の主だよ」
「宿っておられると申しますと……?」
「わしの体を直接あらわさずに、他の者の体を借りているのだ」
「この者の霊魂はどうなっております?」
「わしが表面に出る時は、その踏台の役をつとめているに過ぎぬ。わしが引っ込むときは、彼自身として体にあらわれてくる」
「あなとこの祠の主とは、何かご関係がおありなのですか」
「因縁によって、わしがこの祠の主を守ってやっているのだ。この祠の主ははなはだ汚れた者であるが、その罪ほろぼしに、ここにいて、相応の人を助けたい志望をもっているのである。それに現界にいる時分、この者にすでに改心のきざしがあったに拘らず、わしがこの者の悪事を極端にてき発して苦しめたことがある。このことは、あとになってから、気の毒だった、やり方が苛酷だった、愛が足らなかったと非常にわしを悔いさした。その因縁によって、わしは今ここでこの者を蔭ながら守護し、指導してやっているのである。わしが去ると、純粋にこの者自身となるから、よく注意して見ておるがよい」
「ちょっとお伺いいたしますが、あなた様はなんの必要があって、私をここへお引きつけになったのでございますか」
「お前に、化神ということを如実に知らせようと思ってじゃ」
「ヘェ……」
「化神というのは変化の神ということで、ある他の体ーー大抵はずっと格の下のーーを借りて宿っている、すなわち変装している神霊ということだ」
「格を落としてのお働きはお苦しいでございましょうな」
「むろん、だが、これもわしのめぐりじゃ」
「あなたさまにもまだめぐりがございますか」
「けがれ果てた地上の守護に任じ、それと接触せる霊界に出入りしているのは、地上との因縁がまだ切れきらぬからだ」
「宿命的に自分の身にくっついている環境はめぐりによるのですか」
「そうだ」
「霊界の広さはどれほどありますか」
「無限だ」
「天国も地獄もそれぞれ上中下三段に別れているということを聞いていますが、そうでございますか」
「大別して各三段、あるいは五段、あるいは七段というだけで、中別、小別すれば無限の段階があるのだ」
「地獄へおち入ったなら、もう再び浮かび上がることが出来ないと申しますが、そうですか」
「そんなことはない。改心すれば、かならず向上してくる」
「どういうことが改心でございますか」
「神を信じ、神をみとめ、神に従うことだ。他力の中の自力であることを知ることだ。一切のもののために、相応の奉仕をすることが、真の生活であることを悟ることだ。天国的の人と地獄的の人とは、より奉仕的であるか、より利己的であるかによって分かれる」(『信仰覚書』第七巻 出口日出麿著)
東海教区特派宣伝使 前田茂太