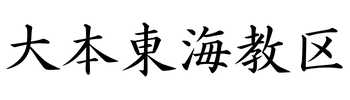動物の使命
陸上の動物は、人間に奉仕し、その活動を支える役割を担っています。そして、この使命を果たすために創造された存在と考えられています。一方、人間は神に仕える存在として、神の意志を受け継ぎ、天地の秩序を整える重要な役割を果たすために創られ、生まれてきたとされています。動物は、その人間の働きを補助するために存在すると位置づけられています。
また、人間が神を崇め敬うように、動物もまた本能的に人間を尊く感じるように創られているとされています。例えば、牛の大きな目は、一見すると人間に恐れを感じさせるかもしれません。しかし、牛の目から見る人間の姿は、まるで神のように尊く映ります。
動物は本能的に人間の役に立つことを望み、より多く奉仕することで霊的な成長を遂げるとされています。その結果、死後には「動物の天国」に行き、やがて進化して人間に生まれ変わる希望を持っています。一方、水産動物は陸上動物とは異なる使命を持っており、人間の食料となることが創造の目的とされています。このため、人間が水産動物を食べることは罪でも不道徳でもなく、自然な行いであるとされています。
また、動物の一生が進化の過程であることを考えると、虫一匹といえども粗末に扱うべきではありません。神諭には、「世界の神、仏、人民、鳥類、畜類、昆虫(むしけら)までも助ける、至仁至愛(みろく)の御用であるぞよ」と記されています。このように、生きとし生けるものを大切にする精神を持つことが求められます。
大本のお示し
陸上の動物は、人間に奉仕してその補助機関たる使命をつくすにある。そしてすべてはこの使命遂行の用のために作られている。したがって動物がどんなに大きな体をしていて力が強くとも、人間は決しておそれる必要はない。
人間は神様に仕えて、神様の次に位して、神意を奉戴して天地経綸の大神業に奉仕するために作られており、生まれて来ているが、動物はその人間の天地経綸の仕事を補助するために作られており、生まれて来ている。
したがって、人間が神様を尊く崇むように、動物はすべて人間が尊く見えるようにできているのだ。例えば牛は、大きな眼をしているので人間は牛をおそろしく思うかもしれないが、いづくんぞ知らん牛の眼から人間を見れば、人間が神様の如く尊く見えるのだ。そう見えるように初めから作られているのである。
それで動物は、一つでも人間のご用をつとめたいと希望するもので、また一つでも余計に人間に仕えたものは死後動物の天国へ行くものである。また水産動物は陸上動物と異なり、人間の食料となる使命をもっている。したがって人間が水産動物を食べるのは、罪悪でもなんでもなく正しいことである。(『木の花』誌昭和二十六年二月号「聖師如是我聞」)
国治立大神は、あらゆる神人を始め禽獣虫魚に至るまで、その霊に光を与へ、いつまでも浅ましき獣の体を継続せしむることなく、救ひの道を作り律法を守らしめて、その霊を向上せしめ給へり。ゆゑに禽獣虫魚の帰幽せしその肉体は、決して地上に遺棄することなく、ただちに屍化(しけ)の方法によつて天にそのまま昇り得るは、人間を措(を)いて他の動物に共通の特権である。猛獣はいふもさらなり、烏、鳶、雀、燕その外の空中をかける野鳥は、決して屍を地上に遺棄し、人の目に触るることのなきは、みな神の恵みによりて、ある期間種々の修業を積み、天上にのぼり、その霊を向上せしむるゆゑなり。ただ死してその体(たい)躯(く)を残す場合は、人に鉄砲にて撃たれ、弓にて射殺され、あるいは小鳥の大鳥に掴み殺され、地上に落ちたる変死的動物のみ。その他自然の天寿を保ち帰幽せし禽獣虫魚は、残らず神の恵みによりて、屍化(しけ)の方法により、天上に昇り得るごときは、天地の神の無限の仁慈、偏(へん)頗(ぱ)なく禽獣虫魚に至るまで、依怙(えこ)なく均霑(きんてん)したまふ証拠なり。ただ人間に比べて、禽獣虫魚としてのいやしき肉体を保ち、この世にあるは、人間に進むの行程であることを思へば、吾人はいかなる小さき動物といへども、粗末に取り扱ふことはできないことを悟らねばならぬ。その精神に目覚めねば、真の神(み)国(くに)魂(だま)となり、神心となることは到底できない。また人間としての資格もない。
かく曰はば人あるいは言はむ。魚を捕る漁師なければ、吾ら尊き生命を保つ能はず、獣を捉ふる猟夫なければ、日常生活の必要品に不便を感ず、無益の殺生はなさずといへども、有益の殺生はまた已むを得ざるべし。かかる道を真に受けて遵守することとせば、社会の不便実に甚だしかるべし、との反対論をなす者がキツと現はれるでありませう。しかし各自にその天職が備はり、猫は鼠を捕り、鼠は人類の害をなす恙(つつが)を捕り食らひ、魚は蚊の卵孑孑(ぼうふり)を食し、蛙は稲虫を捕り、山猟師は獅子、熊を捕り、川漁師は川魚を捕り、海漁師は海魚を捕りて、その職業を守るは、みな宿世の因縁にして、天より特に許されたるものである。ゆゑに山猟師の手にかかる禽獣はすでに天則を破り、神の冥罰を受くべき時機の来たれるもののみ、猟師の手にかかつて斃(たふ)れることになつてゐるのである。海の魚も川魚も皆その通りである。
しかるに現代のごとく、遊猟と称し、職人が休暇を利用して魚を釣り、官吏その他の役人が遊猟の鑑札を与へられて、山野に猟をなすがごときは、実に天則違反の大罪といふべきものである。自分の心を一時慰(なぐさ)むるために、貴重なる禽獣虫魚の生命を断つは、鬼畜にも優る残酷なる魔心と言はなければならぬ。人にはおのおの天より定まりたる職業がある。これを一意専心に努めて、士農工商とも神業に参加するをもつて、人生の本分とするものである。(『霊界物語』第三十二巻 出口王仁三郎著)
輪廻転生
あらゆる存在は、輪廻転生の原理に基づいて形を現しています。例えば、動物は畜生道に堕ちた霊がその姿を変えたものと考えられています。そして、動物たちは向上し、人間に生まれ変わることを望んでいるとされています。
動物には、愛護されているものもいれば、虐待されているものも存在します。一見するとこの状況は不公平に見えるかもしれません。しかし、虐待されている動物はその経験を通じて霊的な修行を積み、次の段階へと向上できる可能性があると考えられます。一方で、人間が動物を特別に愛護することで、その修行が完成せず、死後再び動物界に戻ってやり直さなければならない場合もあります。
このため、表面的には愛護に見える行為であっても、霊的な観点では一種の妨げ、ひいては虐待となることもあります。
現在の世の中では、動物愛護よりもむしろ、人間自身が畜生道に堕ちる危険性の方が大きいと指摘されています。そのため、人間を救済することがより急務であると考えられます。
大本のお示し
一切のものは輪廻転生の理によって形を現わしておる。動物は畜生道に堕ちた霊がそこに現われておる。ゆえに動物は向上して人間に生まれかわろうとの希望をもっておるものである。愛護されている動物、虐使されている動物、一見はなはだ不公平のごとくみえるが、虐使されつつある動物は、その修行を経ねば向上することが出来ないようにできておるのであるから、人間がことさらに愛護するということになれば、修行が完成せられないで、死後ふたたび動物界に生まれてきて、修行の仕直しをせねばならぬことになる。ゆえに形からみれば愛護であっても、その霊性から考えると、一種の虐待になる。今日の世の中は動物愛護よりも、神の生宮たる人間で畜生道に堕ちようとする危険のものがたくさんあるから、この方を救うてやることが、より急務である。動物愛護会などは形にとらわれたる偽善である。いかんとなれば多くの人はそれを食物(くいもの)にしようとしておるから。(『月鏡』 出口王仁三郎著)
進化論のいうがごとき、人間は決して猿から進化したものではない。初めから神は、人は人、猿は猿として造られたものである。
動物が進化して人間になるということ、すなわち輪廻転生の理によって、動物が人間になるというのは、霊界において進化して、人間の性をもって生まるるのである。「霊界物語」の中には一国の有力者を動物化して示したところもある。(『玉鏡』 出口王仁三郎著)
猿であろうと犬であろうと、猫であろうと虎であろうと、すべてこの地表上の諸動物が進化したものが人間である。
なるほど、人間の形体は便宜上、ながい間に祖人猿のごときものから進化したのかもしれない。しかし、その魂は昨日の牛が今日の人間にもなり得るのである。
すなわち、われわれ普通の人間と呼んでいるものの霊魂そのものは、あらゆる動物からきているのであって、いわゆる転生輪廻ということは事実である。(『信仰覚書』第八巻 出口日出麿著)
動物の心性
心は人間だけでなく、動物や植物、さらには自然界のさまざまな存在にも宿っていると考えられています。人が死ぬと霊界に行き、その想念は現界に影響を与えることがあります。
動物たちにも霊的な力が宿っており、その影響は非常に強力です。動物をいじめたり殺したりすることで、その影響が人間に返ってくることもあるとされています。
大本のお示し
動物には五情のうち、覚る、畏るの二情しかはたらかぬ。省みる、恥ずる、悔ゆるの三情は全然働かぬのである。だから破廉恥なっことを平気で行うのである。人の心を覚って用を便じたり、叱られるとこわいということは知って逃げたりするが、その外の情は働かぬ。人にして、もし破廉恥心が無いならば動物と選ぶところがないではないか。(『月鏡』 出口王仁三郎著)
心は人にも他の動物にも植物にもある。日地月星にも心がある。うすい濃いの差があるのみである。人間が死ねば、霊は目に見えぬ世界にゆく。そうしてそこから現界へひびいてくる。怨霊などはその家や人をねらう怨みの霊であるが、これもあるのである。往々、医者、ことに解剖学者や動物試験などで小動物を殺す家庭、人の怨みをうける家などうまくゆかないのは、みなこの霊のなす業である。(『信仰雑話』 出口日出麿著)
動物の心霊でも非常な働きをするものであって、たとえばネズミなどは火事がある二、三日前にちゃんと他所(よそ)へ移ってしまう。大火のある前にネズミがおらなくなった、ということはよく聞くことです。また山にいるキジとか、あるいはいろいろな動物などは、大地震がくる前にさわぎだして移転する、そういう時には用心せよ、と古来、言いつたえがあります。これは、いわゆるそれを感じるのであります。ただ人間は外界のことにとらわれ過ぎるために、そういう力が鳥、獣におとっている人が近代は多いのです。
犬などでも、シェパードなどは百メートル半径以内に人が来ると、ちゃんと知っています。向こうがわに寝ておって、こっち側を人が歩いて来てもすぐに嗅ぎわける、そういう力を持っています。それは、鼻の力というほかに心霊の力があるのであって、本能的に動物にそなわっています。ガマなどはハエが飛んでいると口を開けてパクッと吸い込む。すぐそばでなしに、だいぶはなれておっても吸い込む。イタチやテンなどは鶏の血を吸うのに、鶏小屋の外から吸うて殺したりすることはよくあります。こういう威力を持っているだけに、もしそういう動物の霊魂が死後もこの世に残っておるとすれば、それが人間におよぼす影響というものは大変に大きいもので、動物をいじめたり、なんにもしないのに殺すということは、いかに罪悪であり、それがまた人間にかえって来て人間を苦しめ、人間をいろいろと困らせているということは思いなかばに過ぎるものがあります。(『信仰叢話』 出口日出麿著)
東海教区特派宣伝使 前田 茂太