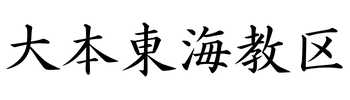正食
「正食」とは、「正しい食生活のあり方」です。正しい食生活とは、四季それぞれの時季に、その土地で産出された食物を食べる「季節食」や、「国土食」(地産地消)などの自然に適った食生活のことです。生活習慣病をはじめ、病と毎日の食生活は深い関わりを持っています。
生活習慣病の予防や、患っている病気の重症化を抑え改善するためには、正しい食生活を心掛けることが大切です。
出口王仁三郎聖師は穀菜食について、「米は陽性のもので、これを常食すれば勇気が出る、そして陽気である」「野菜を食えば仁の心が養われる」「ゆえに野菜を常食とする日本人にして初めて愛善の心がある」と、穀菜食は肉体だけでなく霊魂も育てると示しています。
マクロビオティック
鎌倉時代以降、仏教、禅宗により伝えられた、魚介類や肉類を用いず、穀物・野菜などを主とする精進料理は、和食(日本料理)の起源とされています。
最近では、「マクロビオティック」という、穀物や野菜、海藻などを中心とする和食(日本料理)をベースとした食事を摂ることにより、自然と調和をとりながら健康な暮らしを実現するという考え方が、ハリウッドスターやスーパーモデルなどに支持されています。
「まごわやさしい」
和食(日本料理)の食材の頭文字を合わせたもので、「まごわやさしい」という言葉があります。エネルギー源となる炭水化物、体をつくるたんぱく質、体の調子を整えるビタミン、ミネラルが豊富な食材です。
ま:「豆類」
ご:「ごま」
わ:「わかめなどの海藻類」
や:「野菜」
さ:「魚」
し:「しいたけなどのきのこ類」
い:「芋類」
これらの食材は、取り入れることで生活習慣病の予防、コレステロールの低下、老化予防など健康的な生活を送ることができます。
コオロギは危険な食材なのか?
2018年9月21日に内閣府食品安全委員会は、コオロギ食の安全性に関して懸念を表明する資料を公表しています。この情報を参考にして、食品の安全性や衛生状態についてよく確認することが重要です。
コオロギの生体内には、好気性の一般細菌に加え、耐熱性の芽胞形成菌(例:セレウス菌)が存在することが知られています。これらの菌は特に高温下で生存しやすく、適切な加熱処理が行われていない場合、感染や食中毒のリスクがあります。
また、コオロギには、エビやカニなどの甲殻類アレルギーを引き起こすトロポミオシンというタンパク質が含まれており、アレルギー症状を引き起こす可能性があります。
ただし、現在の食品表示の規則では、小麦、卵、大豆などを含む28品目以外のアレルゲンは表示枠内に記載することができません。
したがって、コオロギに含まれるアレルゲン成分は明示されない可能性があります。アレルギーを持つ人やアレルギーのリスクがある人は、慎重に摂取する必要があります。
コオロギ食を摂取する際には、上記の注意点を頭に入れ、個人の健康状態やリスクに合わせて適切な判断を行うことが重要です。
欧州食品安全機関(EFSA)、新食品としてのヨーロッパイエコオロギ(Acheta domesticus)についてリスクプロファイルを公表
資料管理番号ID:syu05010960149
2018年9月21日欧州食品安全機関(EFSA)は8月28日、新食品としてのヨーロッパイエコオロギ(Acheta domesticus)についてリスクプロファイルを公表した(7月6日採択、PDF版15ページ、doi.org/10.2903/j.efsa.2018.e16082)。概要は以下のとおり。
このプロファイリングは、EU加盟国のリスク評価機関に所属する若手研究者育成を目的としたEU‐FORA (The European Food Risk Assessment Fellowship)プログラムの一環として、スウェーデン農業科学大学(Swedish University of Agricultural Sciences)により実施されたものである。食糧農業機関(FAO)は、今後予期される需要を満たすためには、世界の農業生産が70%増加する必要があると予測している。栄養価の高い昆虫は、特に動物性タンパク質の重要な供給源として、増加する食糧需要に向けて重要な役割を果たす可能性がある。欧州が食用昆虫市場として急成長を遂げていることを示す市場調査もあり、需要の高さから、直翅類(バッタ目)の利用が進むと期待されている。新食品規則(EU) 2283/2015に基づき、昆虫及び昆虫由来製品は新食品と見なされ、新食品承認の対象となる。このヨーロッパイエコオロギ(Acheta domesticus、訳注:ペットとして飼育されている両生類・節足動物・鳥類の餌として広く繁殖されている)を対象とするリスクプロファイルは、当該昆虫のヒトによる喫食を意図している。
リスクプロファイルでは、野外コオロギ繁殖場と対照して、HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Points)及びGFP(good farming practices)に基づく屋内ヨーロッパイエコオロギ飼育システムを想定している。利用した方法論には文献スクリーニング、可能性のあるハザード特定が含まれ、更に、得られたエビデンスに対して関連のある算入基準を組み込んだ。これらの基準には、農場はOne Health原則(訳注:人の衛生、家畜の衛生、環境の衛生の関係者が連携して対策に取り組むべきであるという理念)に向かうべきとの理念のもと、ヨーロッパイエコオロギの全生存期間に渡り、家畜衛生及び食品安全の側面が含まれる。データ不足の場合は、直翅目属の近縁種(バッタ、イナゴ、他種コオロギ等)の対応するエビデンスを利用している。しかしながら、動物衛生と食品安全において、著しいデータギャップが存在している。HACCPタイプのシステムが実施された場合でも、リスクプロファイルにおいて以下に挙げる相当な懸念が特定された。(1)総計して、好気性細菌数が高い。
(2)加熱処理後も芽胞形成菌の生存が確認される。
(3)昆虫及び昆虫由来製品のアレルギー源性の問題がある。
(4)重金属類(カドミウム等)が生物濃縮される問題がある。
寄生虫、カビ類、ウイルス、プリオン、抗菌剤耐性及び毒物類等の他のリスクは低いと判定された。数種のリスクに関しては、更なるエビデンスが必要であることを強調しておく。
当該文書は下記URLより入手可能。
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.e16082
大本のお示し
食物の影響これも専門的にいいますと、なかなかむつかしくなりますが、元来、日本人は西洋人と違って血が清らかである。今まで、あまり肉を食わなかった人種であります。気候の点からいっても、獣肉類はそう日本人にはふさわしいものではないのであります。このごろは医者はあまり肉食をすすめなくなりましたが、ああいうものは「精」が強い。一時は養分になりますが、それだけ毒になりやすい。腸の中で腐るというと非常な毒となることがある。
肉類を多く食う人は性欲が強かったり、気持ちが暴(あら)かったり、忍耐力がなかったり、そういう結果になりやすいものである。概していえば、植物性の物を主にした方がほんとうである。また食物というものは、みな気がはいっている。そこにらっきょうがあっても、みかんがあっても、米があっても、みなその土地の気を含んでいる。植物独得の性能によって、それを吸い寄せている。その気を人間が食うのでありますから、栄養は多い。古いものは気がぬけがちですから、新鮮な食物をえらぶことが大事であります。(『信仰叢話』 出口日出麿著)
わたしは柿が大層好きである。果物の中では柿が一番美味しい。柿はまた毒消しの働きをするものであって、夏の暑い時から、秋にかけていろんな悪い食物を食べてた毒が秋になって出てくるのを、柿によって消してしまうようにできているのだ。単に柿のみならず、神様は季節々々に人体に必要なるものを出して下さる。春は人間の体が柔らかになってくるから、筍のような石灰分に富んだものを食べさすようにちゃんと用意してあるのだ。ゆえに人はその季節相応のものを食べておれば健康を保つことが出来るようになっているものである。今のように夏出る西瓜を春ごろ食べてみたり、春出るべき筍を冬食べて珍味だと喜んでいるのは間違っている。それだから人間がだんだん弱くなってくるのである。すべてが間違いだらけである。(『水鏡』 出口王仁三郎著)
魚は智的食物、野菜は仁的食物、米は勇的食物で、其食する処に従つて性格にも変化を来すものである。(『玉鏡』 出口王仁三郎著)
動脈硬化症より免がれむとする者は、断然肉食を止して菜食に移らねばならぬ。魚類等もなるべくは、さけたがよい。殊に刺身の類はよろしくない。たまにはアツサリした河魚ぐらゐは食べてもよい。元来世人は肉類魚類には多大の滋養分がある様に思うて居るが、真の滋養価は野菜が一番である。かなり大きい鯛と大きな大根一本と相応する位なものである。(『玉鏡』 出口王仁三郎著)
『又、食物を大気津比売の神に乞ひたまひき』
食物(ヲシモノ)の言霊返しは、イである。イは命であり、出づる息である。即ち生命の元となるのが食物である。またクヒ物のクヒはキと約(つま)る。衣服もまた、キモノといふのである。キは生なり、草なり、気なりの活用あり。ゆゑに衣と食とは、生命を保持する上にもつとも必要なものである。ゆゑに人はヲシ物のイとクヒ物のキとによつてイキてをるのである。また人の住居をイヘといふ。イヘの霊返しはエとなる。エは即ち餌であり、胞である。要するに、衣食住の三種を総称して食物と言ひ、エと言ひケといふのであります。
大気津姫といふ言霊は、要するに物質文明の極点に達したるため、天下こぞつて美衣美食し、大厦高楼(たいかかうろう)に安臥(あんが)してあらゆる贅沢をつくし、体主霊従の頂上に達したることを大気津姫といふのであります。糧食(かて)の霊返しは、ケとなり、被衣(かぶと)の霊返しはケとなり、家居(かくれ)の霊返しはまたケとなる。ゆゑに衣食住の大いに発達し、かつ非常なる驕奢(けうしや=※ぜいたく)に、世界中がそろうてなつて来たことを大気津姫といふのであります
『乞ひたまひき』といふのは、コは細やかの言霊、ヒは明らかの言霊である。要するに、素盞嗚尊は八百万の神に対して、正衣正食し、清居すべき道をお諭しになつたのを『乞ひたまひき』と、言霊学上いふのであつて、決して乞食が食物を哀求するやうな意味ではないのであります。(『霊界物語』第一一巻第一五章 出口王仁三郎著)
昔から正月の七日の行事に七草粥といふのがあつて「七草なづな、唐土の鳥が、日本の国へ渡らぬ先に……」と囃しながら七草をたたいて、それをもつて粥を作り一家が食する習慣があるが、是は一方食物の用意をせよとの神意であるけれど、又一方には菜食の必要を説かれたるもので、唐土の鳥が渡らぬ先、即ち外国の飛行機の襲来に備ふる為め、菜食して肉体的の抵抗力をつくつておけと云ふ事なのである。かうした非常時に際して、平常から菜食して居る人のより強さを十分知る事が出来るであらう。(『玉鏡』 出口王仁三郎著)
東海教区特派宣伝使 前田茂太