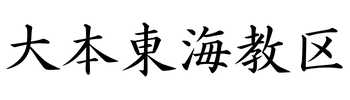祝詞とは
祝詞は、神さまに奏上される祈りの「言霊(ことたま)」であり、神道において古来から非常に重要視されてきました。
特に大祓祝詞は「中臣の祓」とも称され、日本人の古来からの信仰や価値観に深く根ざしています。この祝詞は、心身の穢れや災厄の原因となる罪穢れや過ちを祓うためのもので、人々はこの祝詞を通じて自己浄化を促し、清らかな心身を保つことを追求してきました。大本では、大祓祝詞を「神言」と呼び、毎日奏上しています。
祝詞は日本の文化や信仰において、人々の精神的な成長や心の安寧に欠かせない役割を果たしてきました。祝詞は神明の心を和らげ、天地人の調和をもたらす素晴らしい言霊です。
ただし、その言霊が円満で晴朗であることが求められ、それによって初めて一切の汚濁と邪悪を払拭できます。逆に、悪魔の口から発せられると、世の中はますます混乱し悪化します。なぜなら、悪魔が使用する言霊には世界を清める力がなく、欲望、嫉妬、憎悪、羨望、憤怒などの悪念によって濁っており、天地神明の御心を損なうからです。日本は「言霊の幸わう国」と言われていますが、身も魂も真に清浄となった者がその言霊を使うことで初めて、世の中を清めることができます。反対に、身魂が汚れた者が言霊を使うと、その言霊には邪悪な要素が含まれているため、世の中はかえって暗黒に陥ります。
※言霊=日本人が古来より信じてきた言葉に宿る霊的な力。
大本のみ教え
宇宙にはアオウエイの五大父音が間断なくなり響いているが、人々が発する正しからざる言霊によって之が濁るのであるから、常に天津祝詞を奏上して、音律の調節を行なうのである。(『玉鏡』 出口王仁三郎著)
今日の牧師に一番惜しむべきは、ヨハネ伝福音書の第一章が真解できぬところである。「大初に道(ことば)あり、道は神と偕(とも)にあり、道(ことば)は即ち神なり」とあるが、言葉すなわち道は充ち満つるの意味で高天原のことである。この天地は言霊の幸う国で言葉はすなわち神である。祝詞や祈りの言霊によって、よい神が現われるのである。声の澄んだ人ほど魂はよい。(『玉鏡』 出口王仁三郎著)
天地も家もわが身も人の身も清めきよむる神の祝詞(ほぎごと)(『大本の道』 出口王仁三郎著)
大祓の祝詞は世に存在しても、その意義すら分らず、従つてその実行が少しも出来てゐなかつた。その大実行着手が国祖 国常立尊の御出動である。神国人の責務は重いが上にも重い。天地の神々の御奮発と御加勢とをもつて、首尾克(よ)くこの大経綸の衝(しょう)に当り神業に奉仕するといふのが、これが大祓奏上者の覚悟であらねばならぬ。(『霊界物語』第三九巻付録「大祓祝詞解」 出口王仁三郎著)
祝詞はすべて神明の心を和げ、天地人の調和をきたす結構な神言である。しかしその言霊が円満晴朗にして始めて一切の汚濁と邪悪を払拭することができるのである。悪魔の口より唱へらるる時は、かへって世の中はますます混乱悪化するものである。けだし悪魔の使用する言霊は世界を清める力なく、欲心、嫉妬、憎悪、羨望、憤怒などの悪念によって濁ってゐる結果、天地神明の御心を損ふにいたるからである。それゆゑ日本は言霊の幸はふ国とはいへども、身も魂も本当に清浄となった人がその言霊を使って始めて、世のなかを清めることができ得るのである。これに反して身魂の汚れた人が言霊を使へば、その言霊には一切の邪悪分子を含んでゐるから、世の中はかへって暗黒になるのである。(『霊界物語』第一巻 出口王仁三郎著)
すべての祓は、大本の妙(たえ)なる御業(みわざ)にして、第一に神を和(なご)め奉り、心の罪穢(けがれ)、身体の悪を清め、罪科(とが)、過失(あやまち)、疾病(やみ)、曲事(まがごと)、祟(たた)りを祓う大神法(おおみのり)である。人たるもの軽々しくみのがし、うち捨ておいてはならぬ。(『道の光』 出口王仁三郎著)
人間は幽界から現界へアクぬきのために送られてきたものだとの説を真なりとするならば、そのアク(悪)さえぬけたら、幽界または神界へ引きとられるはずだから、いつまでも長生きしておる人間は、アクぬけがしないために壮健なのだと思ったら、われながら、わが身があさましくなってくるだろう。しかしながら人間は決して現界へアクぬきのために生まれてきたのではない。神が天地経綸の司宰者または使用者として、現世へ出したものである以上は、一日も長く生きて、一事にても多く神の御用をつとめねばならぬものである。朝夕の天津祝詞や、神言はその日その日の罪科、過ちを祓い清めて天来そのままの神の子、神の宮として神界へ奉仕するとともに、現界においても人間生存上大々的に活動すべきものである。(『月鏡』出口王仁三郎著)
われわれが始終にご神前に奏上する大祓祝詞は天孫降臨の次第でもあり、また今の世を祓い給え、清め給え、という言葉でもあります。すなわち言霊の大麻(おおぬさ)であり、塩であります。
つぎに、病者、弱者の身代りになって千座(ちくら)の置戸(おきど)を負う人、これは人の大麻であり塩であります。そういう意味で神柱(かんばしら)というのは、みんなのめぐりを取って、だんだん世を浄(きよ)めていくというご用をしているのであります。(『信仰叢話』 出口日出麿著)
御禊の祓、又中臣の祓を唱ふれば、上は現人神が国を治めらるゝ願ひや、嘉ぎ言より、下は人民が身を治め家を斉ヘるベき祈りより、諸々の災禍罪科の、逃れ亡ぶる願の言葉、充分に連ねられてあるから、別に繰返し、くどき事を神の御前にて並ベる事は要らない。(『道の栞』 出口王仁三郎著)
今後世界を愛し、人類を愛し、万有を愛する事を忘れてはならぬ。善言美詞を以て世界を言向和はす事が最も大切である、神の前のみでなく人の前でも同様に善言美詞を用ひねばならぬのである。神に救はれむとして却(かえ)て神に反(そむ)くことが少くないから、決して他人を排したり非難したりするものでない。祝詞のことばが真の善言美詞であって、実は今の日本語も外国語を輸入した言葉が大部分であるから、中途半端の日本語は決して善い事はないのであって、外国語を排するならば現今の日本語も同様の意味で外国語として排斥せねばならぬ訳になって了ふ。(『出口王仁三郎全集』第二巻)
祈りとは
祈りは、「世界の安寧や他者への思いを込めること、利他の精神、自分の内なる神との繋がりを願い求めること、神など神聖視された存在に対して何かを願うこと」と定義されており、宗教や信仰において最も基本的な行為の一つとされています。
自らの力ではどうにもできない状況に立たされたとき、人間は祈ることしかできません。このような瞬間に真剣に祈ることで、心を穏やかにし、平静をもたらしてくれます。祈りは唯一の救いであり、神さまと人の心が繋がるための道です。
しかし、真剣な祈りは自分の力ではどうにもならない状況に直面しない限り、自然に湧き上がるものではありません。真剣な祈りは、私たちの家庭や社会、そして世界全体の災害や不幸を最小限に抑える力となり、感謝、希望、そして勇気の源となります。祈る行為は、困難な時に希望を抱き、心のバランスを保つための重要な手段となります。
祈りの効果
祈りの効果は実験によって確認されています。カリフォルニア大学で行われた一つの実験では、心臓病の患者393人を192人と201人の2つのグループに分けました。その後、192人のグループにだけ毎日他の人々から祈りを送ってもらいました。その結果、祈りを受けたグループでは9人の病状が悪化したのに対して、祈りを受けなかったグループでは48人も悪化したと報告されています。
ミズーリ州の病院での別の実験では、1000人の患者を2つのグループに分け、一方のグループだけに他の人から祈りを送ってもらいました。その結果、祈りを受けたグループの患者たちは10パーセントも回復が早かったと報告されています。デューク大学による1986年から1992年の実験では、65歳以上の4000人を対象に調査され、毎日祈りをささげている人は祈らない人よりも長生きしたとの結果が出ました。
また、アメリカの民間研究機関スピンドリフトは、1970年代から祈りが与える影響力を研究し、ライ麦や大豆の種子に対して祈りを捧げ、祈った種子とそうでないものを比較しました。その結果、祈りを受けたもののほうが発芽率が高かったことが報告されています。
これらの実験からは、祈りが現実的な効力を持っており、距離や顔見知りかどうかに関係なくその効果が現れることが示唆されています。
出口なお開祖の祈り
開祖さまは、日々御礼なさるには、とにかく自分のことや一家のことを願うようなことは少しもなく、こんどのことは世界の難渋(なんじゅう)であるから、世界の大難を小難にして、少しでもみなを助けていただくようとのお願いばっかりでありました。(二代教主さま 昭和七年二月六日みろく殿にて)(『おほもとしんゆの栞』第四号)
祈りより来る体験
人間は、何にすがって生きていけばよいのでしょうか。よく考えてみれば、たのむべからざるものを頼りにしていることもありましょう。わたくしはかつて、世間的にたよりとするすべてを失ったおもいの日々がありました。人間の力では、どうにもならない苦境におとされたことがありました。そんなとき、おたのみするのは神さまだけでした。巨大(おおき)な壁にぶつかって、自分にはどうする力もないことが分かると、ただ、拝むだけでした。
その後、自分の気持ちが神さまの近くにいるおもいの日もあり、神さまからはなれているような日もありますが、気持ちの根底においては、安心して、いつも神さまといしょに歩ましていただいていると思えるようになったのは、そうした絶体絶命のところに追いこまれて、真剣にお祈りさしていただくことができ、神秘というものにふれさしていただいたからです。
苦境にあって切実に祈り求めた時、与えられるものが太い綱とばかり思ってはなりません。それは、クモの糸のようにかぼそい時もありました。それなのに糸よりも細い神さまからのものが非常なお力になっていただけるのでした。絶望の壁にとざされてみると、糸のようにか細くても、神さまからのものに頼る、それだけで安心していられました。拝むよりほかない苦境にいて、ただ拝んだということだけで、
一条の光明をいただき、それにおすがりすることができました。人の一生には、いろいろのことがあり、一度にいろんな問題がおこることもあります。そうした時は誰でも心がゆれ動くものです。さびしい気持ちになるものです。その時ほんとうの力になっていただけるのは、信仰のおかげでした。拝むことによっていただく、まことに細い糸が、なんともいえない力になりました。(『寸葉集』第一巻 出口直日著)
祈りこそ唯一の救い
祈りこそは唯一の救いであり、神さまと人の心が通い合う道でございます。しかし真剣な祈りは何かことに当たらなければなかなか湧き上がってこないものでございます。
私たちの常々の祈りも荒れ狂う嵐の中における祈りのように真剣でありますとき初めて開祖のご精神に生きることが出来て、私たちの家庭や、また広く社会や、世界の災害や不幸を最小限に止める力となり、感謝と希望と、勇気を起こさせる源となりまして、神さまの願われます、みろくの世へ近づいてゆくことを信じるのでございます。(S34・11・2)(『三代教主御教示集』 出口直日著)
一生のうちには、どうにもならないような部厚い壁につきあたりますが、へいぜいの時でも、その人にとっては、なかなか問題になるものを抱いていられるようです。けれどもこれは、少しも、人間を本質的に暗くするものではないはずで、むしろ、これあることによって、人間は磨かれ育てられ、より安定した明るさをいただけるようにおもいます。私もそのはんちゅうにあるもので、さまざまな問題をかかえながら、一生けんめいに神さまを拝ましていただき、神さまを拝ましてもらっていますと、不思議と安心した、明るい気持ちをいただくことができました。有難いことにご神前に坐るまでは、胸のあたりに、もやもやしていたものが、神さまを拝んでいるうちに、いつの間にかすーっと消えて、胸の辺りが澄んできました。そして、心にゆとりができてきました。
ただ神さまをおがんだだけでは、という方もありますが、やはり先ず拝ましていただくことだと思います。そして心にゆとりをもち、人間的に解決しなければならないものをよく見きわめて、その上で努力していくことでしょう。こうしたところに、わたくしたちの人生にどうしても宗教がなければならないとおもいます。信仰をもっていない人と、信仰をもっている人との根本的なちがいも、そうした日常に、はっきりしてくるとおもわれます。(『寸葉集』巻一 出口直日著)
祈りは希望であり念願
公(おおやけ)のために働こうとしての祈り、本分を尽そうとしての祈り、それは当然であると思います。祈りは希望であり、念願でありますから、そういう念願も希望もない人は、この世になんのために生きておるか、ただボンヤリと生きておるか、私利私欲のためにのみ生きているか、どちらかであります。
そうした念願を、より以上のものに対して述べるということは結構なことでありますが、ただそれを取り違えて、私利私欲に堕すから祈りが往々いましめられているのであります。
祈っていますと、これは人にもより、またいろいろ、その時にもよって違いますが、一種の感応というものがあります。この感応がだんだんはっきりして来るほど信仰は進んでまいります。祈りに要する時と場所は、問うところではないのですけれども、朝夕に祭壇に向かうことは外界的にも精神が統一されやすいのであります。一つの対象をおいて、それに向かうということは、精神を専一にする上において非常な補助になります。ただ何もない所で勝手に祈るよりは統一した気分になれる。そういう所、神に通ずる電話口を設けて、そこへ行くと、何となしに神さまのそばに行ったような気持になるということは、すでに通ずる条件に非常にかなっている。で、そういうことは非常に小乗的なことであり、体的なことであるようでありますが、大事なことであります。(『信仰雑話』 出口日出麿著)
東海教区特派宣伝使 前田茂太