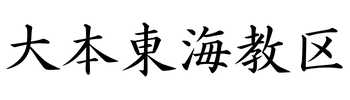仁者愛人
「仁者愛人」は、孟子によって提唱された「離婁下」第二十八章にある言葉で儒教思想における重要な概念です。
「仁者は人を愛し、礼ある者は人を敬す。人を愛する者は、人恒に之を愛し、人を敬する者は人恒に之を敬す」この言葉は、敬愛の精神を表すものとして広く知られており、日本の皇室においても2001年に生まれた敬宮愛子さまの名前の由来となった言葉です。
敬宮愛子さまの名前は、「人を愛し愛され、人を敬い敬われる」ことを願って、「愛子」と「敬宮」と名付けられました。
人間関係や社会での振る舞いにおいて最も大切な心を説いた「仁者愛人」は、他人を思いやり、優しさをもって接することが重要だと説いています。具体的には、他者に対する思いやりと愛情を大切にし、相手の立場や感情を理解することが求められます。
また、「自分が他人にしたこと、言った言葉、取った態度を、同じように他人からされたら、自分はいったいどういう気持ちになるか?」という視点からも考え、自分が嫌なことは他人にもせず、相手の立場も考慮しながら行動することで社会をより良くすることにつながります。
「仁者愛人」の精神を持つことで、相互の愛と尊重が社会全体に広がり、円滑な人間関係や社会の構築に寄与します。この循環する愛と敬意によって、調和のとれた共同体が形成され、争いや不和が減少します。
他者を尊重し共するための普遍的な価値観
「仁者愛人」の思想は、他者への思いやりを実践する心構えを示すものであり、自分の心や行動が他人に与える影響を意識することの重要性を説いています。この考え方は、現代社会においても非常に有用な指針となっています。多様性が広がる今日の世界では、異なる背景や価値観を持つ人々と共存することが一層求められています。
この理念は、文化や信仰、性別といった違いを超えて、他者を尊重し共するための普遍的な価値観と言えます。
この精神を実践するためには、まず “自分も他人も同じように大切に敬い慈しむ”姿勢が必要です。他者を受け入れることは、自己を見つめ直す機会にもなります。たとえば、困難に直面している人に手を差し伸べたり、孤独を感じている人に声をかけるといった行動を通じて、相手への共感が深まり、自身の思いや行動も省みられるようになります。また、誤解や対立が生じた際には、対話を通じて相互理解を図る努力が求められます。
さらに、こうした行動を重ねることで、自己中心的な態度を改めるきっかけが生まれます。たとえば、異なる価値観を持つ人々と意見を交換し、相手の視点を理解する過程で、寛容さや包容力が養われます。これらの姿勢は、個人としての成長だけでなく、調和の取れた社会の構築にも寄与するでしょう。
「仁者愛人」の理念は、現代社会の多様な課題を乗り越えるための有効な手段となり、個人と社会双方の調和をもたらす力を秘めています。
大本のみ教え
惟神的道徳上の義務に服し、天界に奉仕し、自己を制して自己以外に寛大なる神人は、
その実際に於て精神上の自由を有し、一切万事公共の為、何一つ成らざるはなきものである。これに反し、惟神的道徳上の義務を省みず、自己の欲望のみに執 着し、自己に寛大に、他に対して残忍である所の神人は、その実運命の手に縛られてゐるのである。(『霊界物語』第七十五卷 出口王仁三郎著)
いたくない腹をさぐり合っている人々の中にはさまっている程、いやな気持はありません。人間の世界はお互いが反省しなくては……。ほんにわずかな人数のグループでも、なかなか、心の平和は乱されがちです。原因は、お互いの思いやりが足りないこと、また善意の思いやりがすぎて、相手の事情を知らずに独断ですることもあり、むつかしいものです。(『寸葉集』二 出口直日著)
次に、人を許すためには、広く、かつ深く世の中を味わわねばなりませぬ。人の立場というものに同情してやらねばなりませぬ。つねに人に好意をもって接すべきであります。なるべく人の自由意志というものを尊重し、大した害のないかぎりは、これに干渉せぬようにせねばなりませぬ。
人間の生存ということにおいて、哲学や科学は、そうたいして重要なものではありませぬ。またパンがいかほど多量にあっても、常にこれを奪い合っているようなことではなんにもなりませぬ。どうしても、譲りあい助けあい、睦び合うということが、まず第一に必要条件となるのであります。
自分の好きなもののみを愛するということは、鳥獣でもいたします。天地万物を愛して、つねに神に感謝するという心が真に湧かなくては、万物の霊長たる価値はないのであります。(『信仰覚書』一卷 出口日出麿著)
行為の表面のみを観て善悪を云為するのはよくない。心から悪をたくむものはめったにない。みな、その動機には、それぞれのいわく因縁があるのであって、われらは、この動機に同情してやらねばならぬ。すべて、人の行動の原因なるものは、すこぶる微妙複雑なものであって、しかも、その九分九厘までは環境の然らしむるところのものである。だから、人の行動は、あくまでも寛大に見直し聞き直してやるべきである。
世の中には「その人の身になってみれば無理もない」ことが多いのである。ことわざにも「その罪を憎んでその人を憎まず」ということがある。すべて、なしているのではなくして、させられているのであるから、お互いに許しあうことが第一番である。(『信仰覚書』第一卷 出口日出麿著)
世の中の人々が、もう少しお互いに好意をもち合い、晴れやかな寛大な気持ちでつき合ったらとは誰でも思うことであるが、さて、厳密に、日常の自己を内省してみよ、いかに自分というものが利己一方な、狭量な陰うつなものであるかが到るところで発見しえられるであろう。
現界的貴人、高位の人に対しても、なにも、みずから恐れてかかる必要は毫もないし、また、みすぼらしいみなりの人に対しても、決して、最初から軽侮の眼をもって接すべきものではない。すべて起居動作は、いかなる人に対しても、なるべく自然的たるべく、なるままに任したらよいのである。(『信仰覚書』三卷 出口日出麿著)
他人に対してはあくまでも寛大に、しかし、態度としては、時には、わざと怒ったように見せねばならぬ時もある。これは、その人のために、そうした方がよいと思われた場合である。しかし、この時もかならず自利自愛からであってはならぬ。(『信仰覚書』五卷 出口日出麿著)
どんなに寛大にあっても、あとから「ああ、あの時はあまりに寛大すぎた」と悔むことはないが、常にわれわれが後悔するのは、「も少し寛大であればよかった」ということである。
同じ時代に生まれ合わし、同じ地上に住んで、同じ気界に呼吸している以上、目にこそ見えざれ、われわれはお互いに深いふかい因縁の綱によってつながれているのである。お互いが罪人であると自覚する時、われわれは他に向かって「恥を知れ」とか「改心しろ」とかいって迫ることはできない。
この世の一切の罪悪を、連帯責任で、当然われわれは背負うべきである。誰だって、こんな社会になげ出されたら、最後は自殺するか、悪人になり終うせるかより外に途がないのではあるまいか。
一面からいえば、これ明らかに社会の罪である。社会の罪はわれわれの罪である。
しかし、寛大と因循姑息とは全然違う。因循姑息というのは、当然なすべきことをもなさず、いたずらにグズグズしているのをいうのである。
寛大というのは、決して、つねに拱手傍観、逡巡無策のいいではないか。怒るべき時には怒り、叱すべき時には叱するのである。ただその気持に、あく迄も豊かになところがなくてはならない。すなわち、ある事件に対する方便として憤怒し叱責したのであって、決して、その人を憎み、もしくは恨んでいるのではない。一片の私意がなく、毒気をふくんでおらないのである。形式の上では、正しく憤怒であり、また叱責であるけれども、それは色でいえば、かがやいたる淡紅色であって、決して黒色をふくんでいない。だから対者にとって、叱られたわり、怒られたわりには快く感じるのである。
考えてみれば私自身も、今まで幾度となく思わぬ大声を発して人を叱責したおぼえがある。後になって、いつも、恥ずかしいいことをしたと、ちょっとしょげるのだが、妙なことには、私は決して何とも思っていないのに、フトその人の顔を見ていると、なんだか、玉のようなものが一気にのど元へこみ上げてきて、辛抱できないのである。だから後になると、いつも恥ずかしいやら阿呆らしいやらで弱ってしまうのである。しかし、もとより自分として、その人に対してなんとも思っていないので、ケロリウとして直ぐそのあとから話し合っているというわけである。(『信仰覚書』六卷 出口日出麿著)
それから、人に対し周囲に対しての見直し、聞き直しの生活ができるようにならなければ楽天は得られない。自分と同じようにないからといって、人を怒ったり、排斥したりしていたのではこの世に生きてゆけない。ありのまま、なるがままを受け入れて、寛大な、ゆうゆうたる気持ちで天地とともに歩み、天ととともに呼吸し、永遠悠久の道を、永遠悠久の心で、生活する心構えがいります。(『信仰叢話』 出口日出麿著)
東海教区特派宣伝使 前田茂太