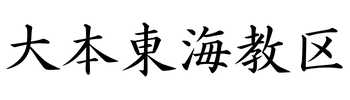「取り違い」 ― 本質を見失った“正しさ”の落とし穴―
取り違いとは、教えの本質を正しく理解できず、自分にとって都合のよい解釈を「真理」だと思い込んでしまうことです。
たとえば、「利他」のつもりが「自己満足」になっていたり、他人への忠告が知らぬ間に「裁き」になっていたりする――そうしたすれ違いが、信仰の歪みを生みます。
私たちは常に、「これは本当に神意にかなっている行いなのか」「この言動はどのような心から出たものなのか」を、常に自分に問い直す必要があります。
信仰とは、固定された「正解」に従うだけでは不十分です。日々変わりゆく状況の中で、自分の心のあり方を省みながら、神さまのみ心にかなう行いを続けるよう努力することです。
ときに、自分の中の小さな驕りや執着に気づくことは、苦しみや迷いを伴います。しかし、それを恐れて目を背けてしまえば、知らず知らずのうちに「取り違い」は拡大し、信仰が本来持つ清らかさを曇らせてしまいます。
だからこそ、私たちは謙虚に、神さまの声に耳を澄ませることが大切です。
信仰とは、他者を導く前に、自分自身の心のあり方を見つめ脚下照顧する意識を持ち続けることです。
「慢心」 ―もうできているという思い込みの危うさ―
慢心とは、自分の信仰や行いが他よりも優れていると思い込んでしまう心の状態です。「自分はもう大丈夫」「他より進んでいる」と思うことで、謙虚な気づきや学びを止めてしまいます。
信仰は、生涯をかけて育む道です。たとえ経験や知識を積んでいても、「まだまだ自分には磨くべきところがある」と謙虚な姿勢で受け止め続ける姿勢こそ、神さまのみ心にかなう歩みといえます。
※慢心についてもう少し詳しく↓
東海教区HPコラム「実るほど頭が下がる稲穂かな」
善意がかえって妨げになることもある
『霊界物語』には、十分に身魂が磨かれていない者が、善意のつもりで神業を妨げたり、事件を引き起こしたりする場面が数多く描かれています。そうした行為の背景には、「慢心」や「取り違い」といった内面的なゆがみが潜んでいます。
たとえ善意であっても、その心が神さまのみ心にかなっていなければ、結果として神意に反した行動をとることになります。自己中心的な動機や、自分の功績・所有に対する執着にとらわれる心のあり方では、知らず知らずのうちに神意から外れた判断をし、「正しいと思っていることが、実は誤っていた」という結果を招いてしまいます。
これは決して他人事ではなく、私たち一人ひとりが陥りうる姿でもあります。常に自分の“動機”を省みる姿勢こそが、内実化につながっていくのではないでしょうか。
「未完成」だからこそ、成長できる
出口王仁三郎聖師は、「人間は神と獣との中間に存在しているので、人間というのだ」と説いています。この言葉は、人間が本質的に“未完成”な存在であること、そして、だからこそ“成長の余地がある”という希望を私たちに示しています。
信仰における真の成長とは、自分の誤りに気づき、その未熟さを受けとめ、少しずつでも改めていこうとする姿勢にあります。そして、その出発点となるのが「省みる心」です。
慢心や取り違いに気づくことは、決して自分を否定することではありません。それはむしろ、自らを神さまのみ心に沿った姿へと改めるための、尊く前向きな機会です。
わたしたちの中には、神さまと同じ性質をもつ直霊「大直日」のはたらきがあります。この直霊の働きを意識し、日々の内省を習慣とすることで、私たちは少しずつ、神さまのみ心にかなった生き方へと近づいていけるのではないでしょうか。
※大直日についてもう少し詳しく↓
東海教区HPコラム「神直日と大直日──神につながる魂」
「省みる」
人は誰しも、自らの歩みや心のあり方に、ふと疑問を抱くことがあります。
「このままでいいのだろうか」「私の言動は、本当に神意にかなっているのだろうか」と。
たとえば、善かれと思ってかけた一言が、後になって「導き」ではなく「裁き」になっていなかったかと気づくこと。
あるいは、誰かのために尽くしたつもりが、よくよく振り返れば自己満足だったのではないかと思い至ること。
こうした気づきの背後にあるのが、自分の行動や心の動機を静かに見つめ直す、“省みる”という営みです。
そんなふうに心を省みるとき、人ははじめて、自分の言動の背後にある「動機」の存在に目を向けるようになります。
ただ、行為として「善」であっても、それがどのような心から生まれたものなのか――そこに信仰の真価が問われます。
「省みる」とは、自らの心の状態や日々の行いを振り返ることです。これは、単に「反省」して落ち込むことではありません。鏡で身だしなみを整えるように、自分の心を映し出して“調律”する、大切な営みなのです。
中には、「反省ばかりしていては前に進めない」「自信をなくしてしまう」といった考えもありますが、それは“省みる”ことの本質を誤解しているのかもしれません。
省みることは後ろ向きな行動ではなく、よりよい自分へと歩んでいくための確かな一歩となります。
省みる習慣こそが、神さまのみ心にかなった生き方へと、私たちを少しずつ導いてくれるのではないでしょうか。
大切なのは、過ちに気づいたときに、自分を責めて終わるのではなく、成長する機会と捉えることです。
省みるとは、決して自分を否定するための行為ではなく、神さまの光に照らし出された自らの姿を受け入れ、そこから歩みを新たにすることです。
この「省みる心」を持ち続けることこそが、内実化につながります。
どんなに信仰年数を重ねても、どれほど人に感謝される行いをしていても、「私は常に神さまの御前にある」という謙虚な思いを失ってはなりません。
大本のお示し
人民というものは、ちよッと行きよると、知らぬ間に、自己の心が上り詰めて居りても判らんぞよ。他人からは能く判るから、取り違いと慢心とが一番に怪我の元となるから、気をつけた上にも気を付けるぞよ。(『おほもとしんゆ』第二卷)
慢神と誤解(とりちがい)が一番こわいぞよ。たれに由らず慢神すると、我の心が大変えらい様に思えて、人から見て居ると、鼻が高うて見にくいぞよ。腹の中に誠さえ在りたなれば、何んな事でも出来るなれど、上から見てよくても心の中に誠が無いと、実地の誠が成就いたさんぞよ。(『おほもとしんゆ』第一卷)
慢神と誤解(とりちがい)が大怪我の元と成るから、是だけに気を付けてやりても解らずに、大きな邪魔をいたす守護神、人民は、腹の中に誠が無いので在るから、ドンナ結構な事を知らしても、心の持ち直しがチットも出来んのは、霊魂の性来が悪いのであるから、根本の心を取り直す事が出来んのを、何うしても今度は取り直しをいたさねば成らんので、神は誠に骨を折りて居るぞよ。(『おほもとしんゆ』第一卷)
神の御用を勤めたと申して、取り違いやら慢神をいたしたら、直ぐに手の掌が変える綾部の大本であるから、誠に気遣いな所の、結構な所であるぞよ。(『おほもとしんゆ』第一卷)
我より偉いものは無い様に思うて、薩張り慢神して了うて、悪の頭に使われて居るのが判らんから、平の人民には、改心がナカナカ難しいので在るぞよ。(『おほもとしんゆ』第六卷)
心のドン底より、神さまの神格を理解し、神の真愛を会得し、愛のために愛を行ひ、善のために善を行ひ、真のために真を行ふ真人間とならなくちや、到底駄目だ。俺たちも少しばかり言霊が利くやうになつて、自分が修行した結果、神力が備はつたと思うてをつたが、大変な間違ひだつた。いづれもみな瑞の御霊神素盞嗚尊様の御神格がわが精霊を充し、わが肉体をお使ひになつてをつたのだつた。これを思へば、人間はチツとも我を出すことはできない。何事も自分の智慧だ、力だ、器量だと思ふのは、いはゆる大神の御神徳を横領いたす天の賊だ。かやうな考へでをつたならば、到底いつまでも中有界に迷ふか、遂には地獄道へ落ちねばならぬ。有難や尊や、神様の御恵みによつてハツキリと霊界の様子を見せていただき、実に感謝のいたりである。これから吾々は、今までの心を入れ替へて、何事も神様にお任せするのだなア。自分の力だと思へば、そこに慢心の雲が湧いてくる。謹んだ上にも謹むべきは、心の持ち方である。(『霊界物語』第四十七巻 出口王仁三郎著)
人間在世の時に於て自らなせる善、自ら信ずる真をもつて、実に自らの胸中より来るものとなし、又は当然自分の所属と信じて居るものは、どうしても高天原に登る事は出来ない。彼の善行の功徳を求めたり、又自ら義とするものは斯の如き信仰を有して居るものである。高天原及び地上の天人は斯の如きものを以て痴呆となし、俗人となして大いに忌避的態度を取るものである。斯の如き人間は不断に自分にのみ求めて、大神の神格を観ないが故に、真理に暗き痴呆者と云ふのである。又彼等は、元より大神の所属となすべきものを、己に奪はむとするが故に、真より天の賊と称へらるるのである。所謂人間は、大神の御神格を天人が摂受するとの信仰、逆らうて居るものである。瑞の御霊の大神は高天原の天人と共に自家存在の中に住みたまふ。故に大神は高天原に於ける一切中の一切である事は云ふ迄もない事である。(『霊界物語』第四十七巻 出口王仁三郎著)
信仰は全く自由なものだ。神の道では取違いと慢心とが一番おそろしい。取違いしていると神の目からは間違いきったことでも、自分は正しい信仰だと思って進んでゆき、他からの忠言も戒めも聞かない。そして行く所までいって遂につき当たって鼻を打ってヤット気がつく。そして後をふりかえって初めて背後の光明をみて驚き正道に立ち帰るのである。ともかく、間違っていても神から離れぬことが大切である。やがては必ず自分から気がつくことがある。間違っているからといってやたらに攻撃してもつまらない。実は皆だれでも取違いのないものはない。今日のところ、まだ本当にわかったものは一人もないのだ。(『玉鏡』出口王仁三郎著)
神諭に「かいしん」「まんしん」という文字がところどころにあるが、改心、慢心とかくのではなく、改神、慢神とかくのが本当である。心を改めるという意味ではなく、今まで仏などを信じていたのを、神の道に改めると言うのである。慢神というのは神をみだすと言うので、それが悪いと仰せられるのである。(『玉鏡』出口王仁三郎著)
あまり吾々は慢神が強いからナ、この世は人間の力で渡れるものなら渡つて見よ。力のない智慧の暗い、一寸さきの分らぬおろかな人間が、えらさうに自然を征服するとか、神秘の扉を開いたとか、造化の妙用を奪ふとか、くだらぬ屁理屈を言つて威張つてをつたところで、今日のやうな浪に遭うたら、毎日日日、船をあやつることを商売にしてをる船頭さまだつて、どうすることも出来やしない。人間は神様をはなれて、なに一つこの世にできるものはないのだ。(『霊界物語』第九巻 出口王仁三郎著)
わが頭に生えた髪の毛一筋だも、あるいは黒くし、あるいは白くし得る力のない人間だ。この真理を理解して初めて宇宙の真相が悟り得るのである。これがいはゆる惟神であり、魔我彦が最善と思惟して採つたやり方は即ち人ながらであつて、神の御目より見たまふ時は慢心といふことになるのである。
要するに真の惟神的精神を理解ともいひ又は改心ともいふ。たとへ人の前にてわが力量を誇り、わが知識を輝かし、わが善を賞し、わが美を現はすとも、偉大なる神の御目より見たまふ時は実に馬鹿らしく見えるものである。いな却つて暗く汚らはしく、悪臭紛々として清浄無垢の天地を包むものである。故に神は謙譲の徳を以て、第一の道徳律と定め給ふ。人間の謙譲と称するものは、その実表面のみの虚飾であつて、いはゆる偽善の骨頂である。虚礼虚儀の生活を送る者を称して、人間社会にては聖人君子と持てはやされるのだからたまらない。かかる聖人君子の行くべき永住所は、概して天の八衢であることは申すまでもない。(『霊界物語』第四十六巻 出口王仁三郎著)
われほど偉い者はないと思うて慢心いたすと、いつの間にやら鼻が高うなり、鼻と鼻とがつき合うて、しまひには一も取らず二も取らず、大騒動を起すぞよ。可哀さうな者であるぞよ。何というても暗がりの人民を助けるのであるから、頭の一つや二つは叩いてやらねば目がさめぬぞよ。神もなかなか骨が折れるぞよ、早く改心いたされよ。神の申すことを素直に聞く人民は結構なれど、今の世はサツパリ鬼と賊と悪魔との世の中であるから、神の教を聞く奴はチツともないぞよ。(『霊界物語』第五十一巻 出口王仁三郎著)
慢心というもののいかに恐ろしいものであるかということを悟らしていただきました。何事をするにも、決してこれに執着や名誉心などを抱いていてはいけません。ただ、その時その時を、赤子のような心になって生かしきればよいのだと思います。少しでも、自分はえらい、人はあかん、というような気持で仕事をしているようなことでは、決してよい結果をもたらすものではありません。無批判に、ただその仕事をなせばよいのだと存じます。(『信仰覚書』第八巻 出口日出麿著)
東海教区特任派宣伝 前田茂太